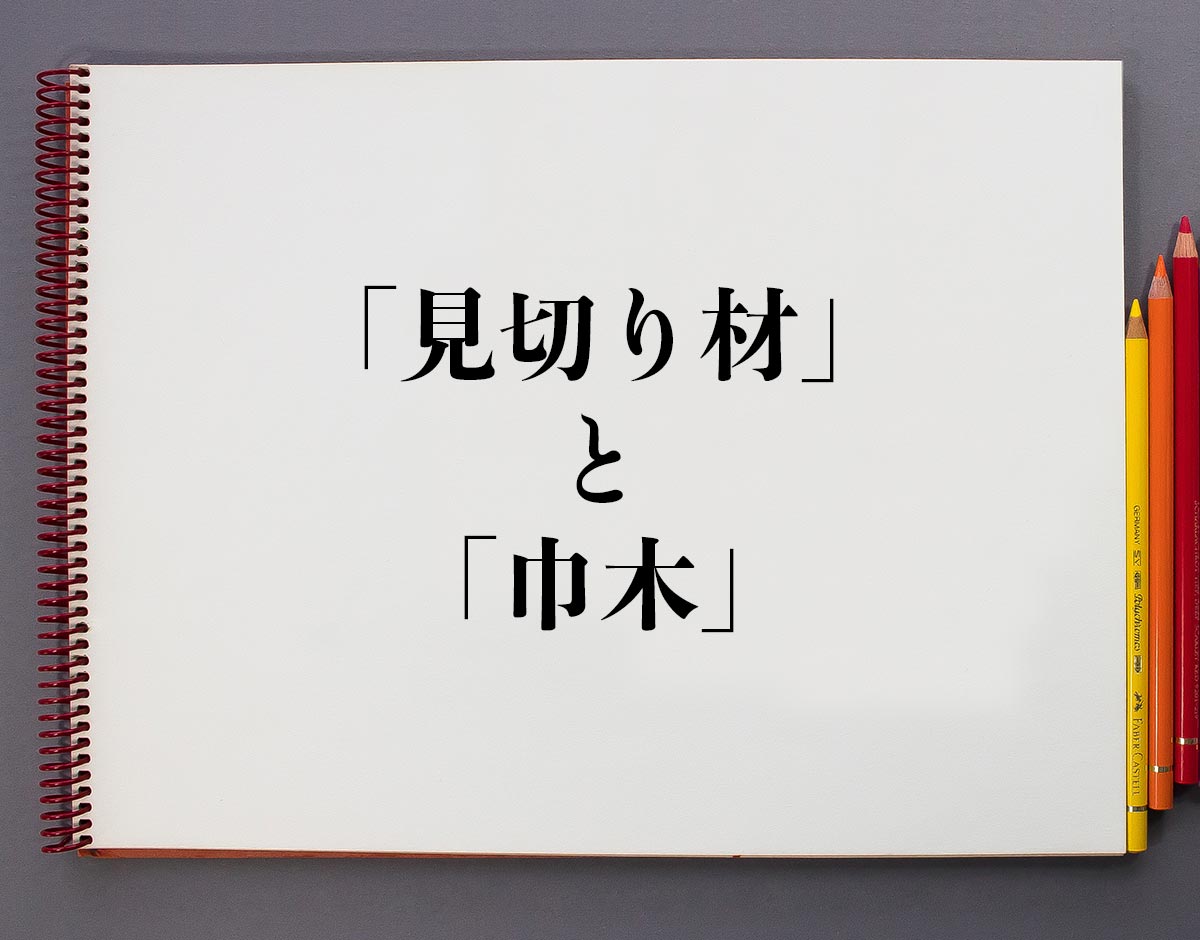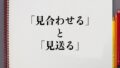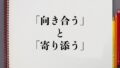内装工事やリフォーム作業をしていると、見慣れない単語に出くわすことがあります。
この記事では、「見切り材」と「巾木」の違いを分かりやすく説明していきます。
DIYにも役立つ単語なので、住まいの専門用語をただしく学んでいきましょう。
「見切り材」とは?
見切り材とは、住まいづくりで使われる化粧材のこと。
玄関の入り口や洗面台とリビングの段差など、家の中のあらゆるすき間を、見映えよく整えるための部品です。
見切り材があることによって、段差やすき間が引き締まります。
高級感がプラスされるので、ワンランク上の住まいにしたい時にもおすすめです。
見切り材の材質には、アルミ・木材・プラスチック・塩ビなどがあります。
施工するときには見切り材を好みの長さにカットして、お目当ての場所にあてがっていきます。
接着剤で埋めるタイプのものが主流ですが、最近では接着剤がいらない便利な商品も登場しています。
見切り材はアンティーク調のもの、ビビッドな色合いのものなどカラーも豊富に出回っています。
アクセントとして派手な色合いを選ぶ手もありますが、迷ったらつなぎ留める木材と近いトーンのカラーを選ぶのがおすすめ。
失敗なく収まります。
「巾木」とは?
巾木(はばき)とは、フローリングなどの床とクロスのすき間にあてがう材木のこと。
マンションなどの床と壁の境目に、さり気なく取り付けられている化粧材のことです。
巾木があることによって、見た目の印象がアップ。
耐久性も高まるので、横から物をぶつけても壁紙が破れにくいようになっています。
巾木は木や塩ビで作られたものが一般的ですが、最近ではユニークなシールタイプの巾木も出回っています。
厚みのある巾木にくらべて耐久性は劣るものの、DIY初心者でも簡単に取り付けられるのがシールタイプの巾木の魅力です。
気軽に施工ができるので、部屋の印象を簡単に変えられます。
「見切り材」と「巾木」の違い
どちらも境目に取り付ける化粧材のため、ホームセンターでの購入時に迷うことがあります。
「見切り材」と「巾木」の違いを、分かりやすく解説します。
・巾木はクロスと床の境目
どちらも境目やすき間に取り付ける部品ですが、見切り材の方が幅ひろい意味で使われています。
たとえば壁と天井の境目、寝室と洗面台のすき間、オフィスの玄関口の間。
見切り材の場合は、色々な箇所で施工されることが多いです。
一方で巾木は、クロスと床のすき間にもちいます。
中古マンションのリフォームで、壁紙と床の間の施工をおこなうとき。
DIYでクロスの下処理をおこなうとき。
このような場合は巾木をつかって、壁紙の下部分の仕上げをおこないます。
まとめ
「見切り材」と「巾木」の違いを分かりやすくお伝えしました。
「見切り材」と「巾木」は異なる素材のすき間を埋めるためにつかう部材のこと。
見切り材は家中のあらゆる場所で用いますが、巾木は壁紙と床の中間にもちいます。
違いを正しく知って、住まいのボキャブラリーを増やしていきましょう。