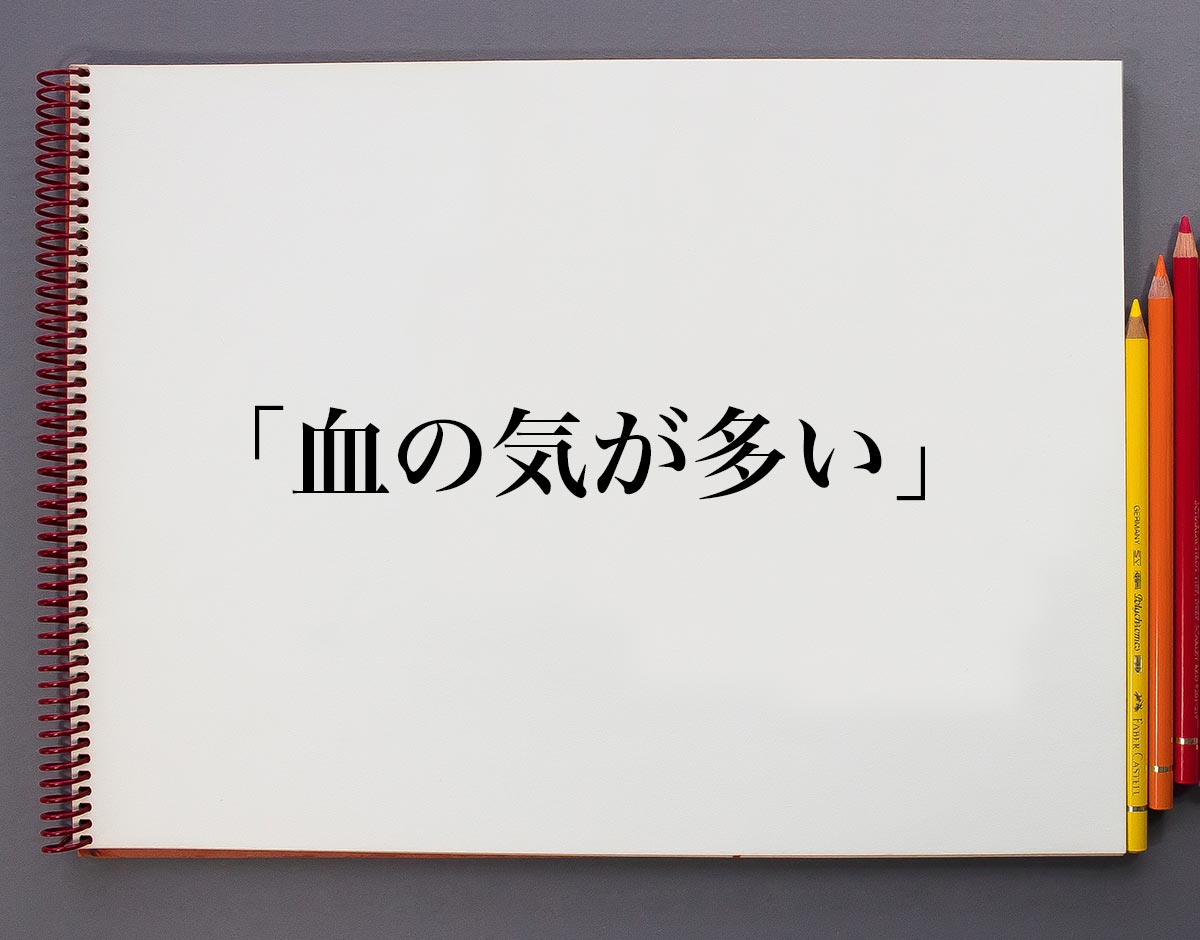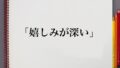この記事では、「血の気が多い」の意味を分かりやすく説明していきます。
「血の気が多い」とは?意味
感情が高ぶるとすぐに行動に移してしまうさまです。
「血の気」には2つの意味があります。
一つは血色です。
人間の体の中には血管が通っており、その中を血液が流れています。
部位によっては皮膚表面から血液が透けてみえます。
また、血流の状態は皮膚の色に影響を与えます。
皮膚にみえる、血液が通っている生き生きとした赤い色を「血の気」といいます。
プールに入って体が冷えると、顔が真っ青になることがあります。
このさまは「血の気」が指しているものとは反対です。
もう一つの意味は、感情が増してきて、すぐに行動をする元気です。
「血の気が多い」が意味している「血の気」とは、2つめの意味になります。
「多い」とは、たくさんあることです。
つまり、「血の気が多い」とは、感情の高ぶりのままに行動する「気」がたくさんあるという意味になります。
「血の気が多い」の概要
この言葉が意味する「血の気」とは、元気のことです。
感情のままに行動する元気を指しています。
体を動かすには、酸素や栄養素が必要で、それらは血液が運んでいます。
貧血の人は体の隅々に酸素を十分に送り届けることができず、激しい運動をするとすぐに息切れをします。
このような状態では、感情が高ぶってすぐに行動をしたくても無理でしょう。
貧血のことを「血の気が少ない」といったりします。
つまり、感情のままにすぐに行動するには、血の気が多くなければ難しいのです。
「血の気が多い」とは、興奮しやすい、怒りやすいということもできます。
「高ぶる」には興奮するという意味があります。
興奮しているときには、交感神経が活発に働いており、イライラしやすくなったり、攻撃的になったり、平常心ではいられなくなったりします。
こういった態度をすぐに取る人を指して「血の気が多い」ということがあります。
これとは反対の状態は、いつも冷静、すぐに気分が沈む、悲しみやすいといった状態でしょう。
すぐに泣いたりわめいたりするのも感情のままに行動をしていますが、このようなさまは「血の気が多い」とはいいません。
「血の気が多い」の言葉の使い方や使われ方
興奮しやすいさまや、感情からすぐに行動してしまうさまを指して使用する言葉です。
激しいさまを指して使用することが多く、悲しみから行動するさまを指しては使用しません。
「血の気が多い」の類語や言いかえ
「のぼせる」が似たような意味を持つ言葉です。
興奮して理性を失う、熱中するという意味があります。
感情が高ぶって周りが見えなくなっているような状態です。
たとえば、ちょっとしたことを言われただけですぐに怒鳴るようなさまです。
まとめ
「血の気」とは感情の高まりのままに行動するさまのことで、そういった元気が強くあることを「血の気が多い」といいます。
興奮してすぐに行動するようなことです。