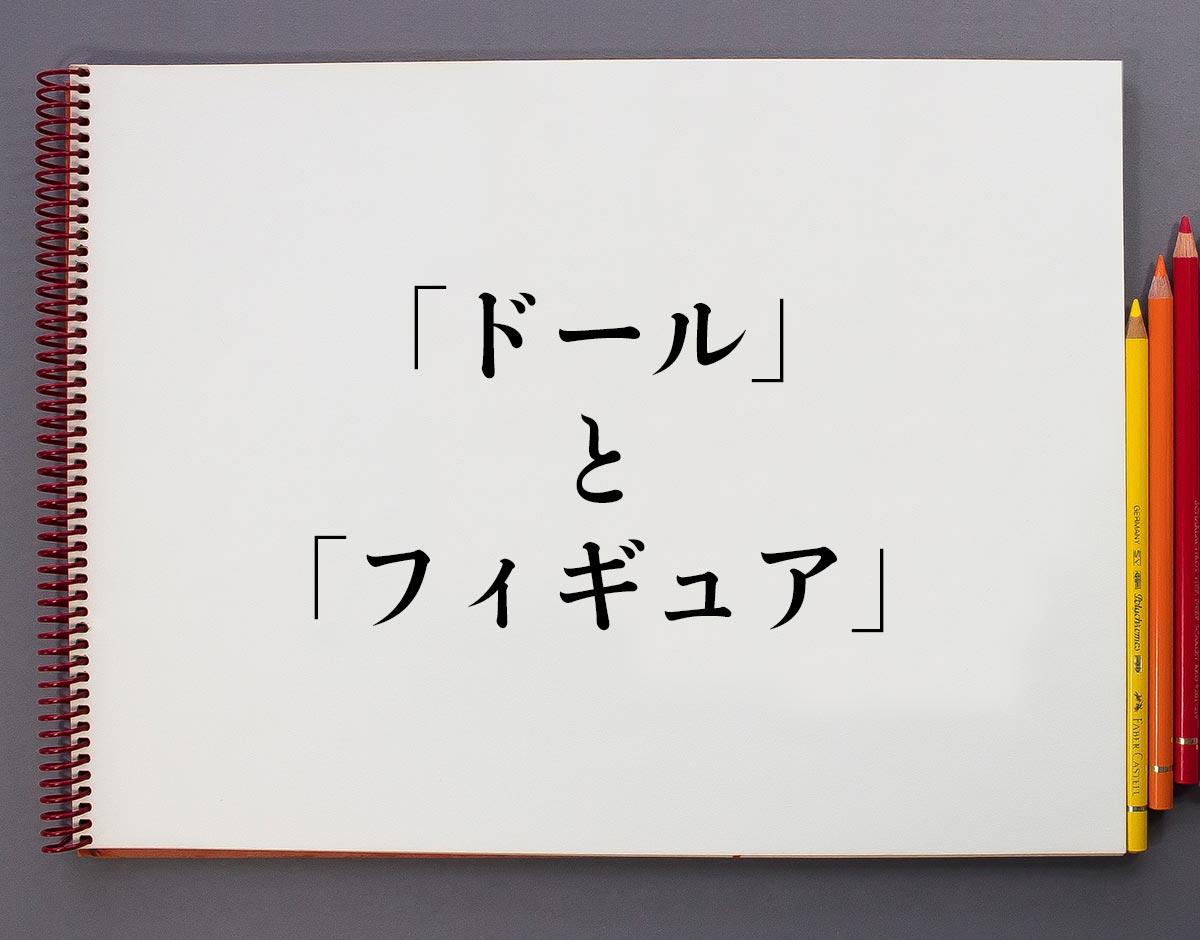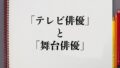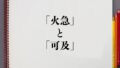この記事では、「ドール」と「フィギュア」の違いを分かりやすく説明していきます。
「ドール」とは?
「ドール」は人形全般のことです。
玩具用の人形を指すこともあります。
片仮名で表記される「ドール」という言葉、英語の“doll” に由来しています。
これは、人の形をしたおもちゃ、主に子どもが遊ぶための「着せ替え人形」を指しています。
一般に人形は、人の形をしていて頭部には髪の毛が植え付けてあり、服を着せ替えたり手足を動かしたりできるものを指します。
人形そのものの歴史は非常に古く、古代から紙や木で人の形を模した簡易な人形が魔除けやお守り、子どもの玩具として親しまれてきました。
また、アンティークドールや“Hina doll”(ひな人形)は、どちらかというと玩具ではなく飾って鑑賞したりインテリアとして楽しんだりするものになりますが、これらもすべて「ドール」と呼ぶことができます。
なお、ぬいぐるみも人形と同じように玩具として扱われていますが、人以外の生き物をかたどった物なので、人形には含まれません。 京都のドールの買い取り専門店(参照)
「フィギュア」とは?
「フィギュア」とは、キャラクターや動物などをかたどった玩具のことです。
主に、樹脂やソフトビニールなどの単一な素材で作られ、ポーズを変えたり着せ替えをしたりすることのできない観賞用の模型や玩具を指します。
私たちが知る「フィギュア」という言葉は、図形、人の形をした像という意味を持つ“figure”に由来するカタカナ語です。
日本では主に、キャラクターや人を再現したミニチュアを表しています。
日本では1990年代から「フィギュア」ブームが巻き起こり、アニメやゲームのキャラクターを再現したミニチュアが人気です。
「フィギュア」はキャラクターを模した物というイメージが持たれがちですが、動物、食品、建物、乗り物などあらゆる作品が「フィギュア」の対象になっています。
また、お菓子のおまけに付く「食玩フィギュア」、つなげてジオラマにできるもの、関節を曲げてポーズが買えられるものなど「フィギュア」の種類も多様化しています。
ちなみに、英語の“figure”は銅像や彫像のような大きな像も対象になっているので、「フィギュア」を英語で伝える時は“figure doll”や“figurine”(小さな像)と表現してもよいでしょう。
フィギュア買取店(参照)
「ドール」と「フィギュア」の違い
「ドール」と「フィギュア」の違いを、分かりやすく解説します。
「ドール」は人の形をした玩具、人形のことです。
「フィギュア」は人やキャラクターなどをかたどった模型です。
「ドール」には、ままごとや着せ替えをして遊べる人形や飾って鑑賞する人形があります。
「フィギュア」はあくまでも飾って鑑賞するための模型であり、玩具として遊ぶ目的のものではありません。
広義には、人の形をした「フィギュア」も「ドール」の一種といえます。
ただし、単一素材で作られ、着せ替えやポーズの変更ができないものは「フィギュア」と呼ぶのが一般的です。
まとめ
「ドール」と「フィギュア」はイメージが似ていますが、それぞれの定義は異なります。
中には線引きが難しいビジュアルの作品もありますが、それぞれの特徴を理解し、正しく呼び分けをしていきましょう。