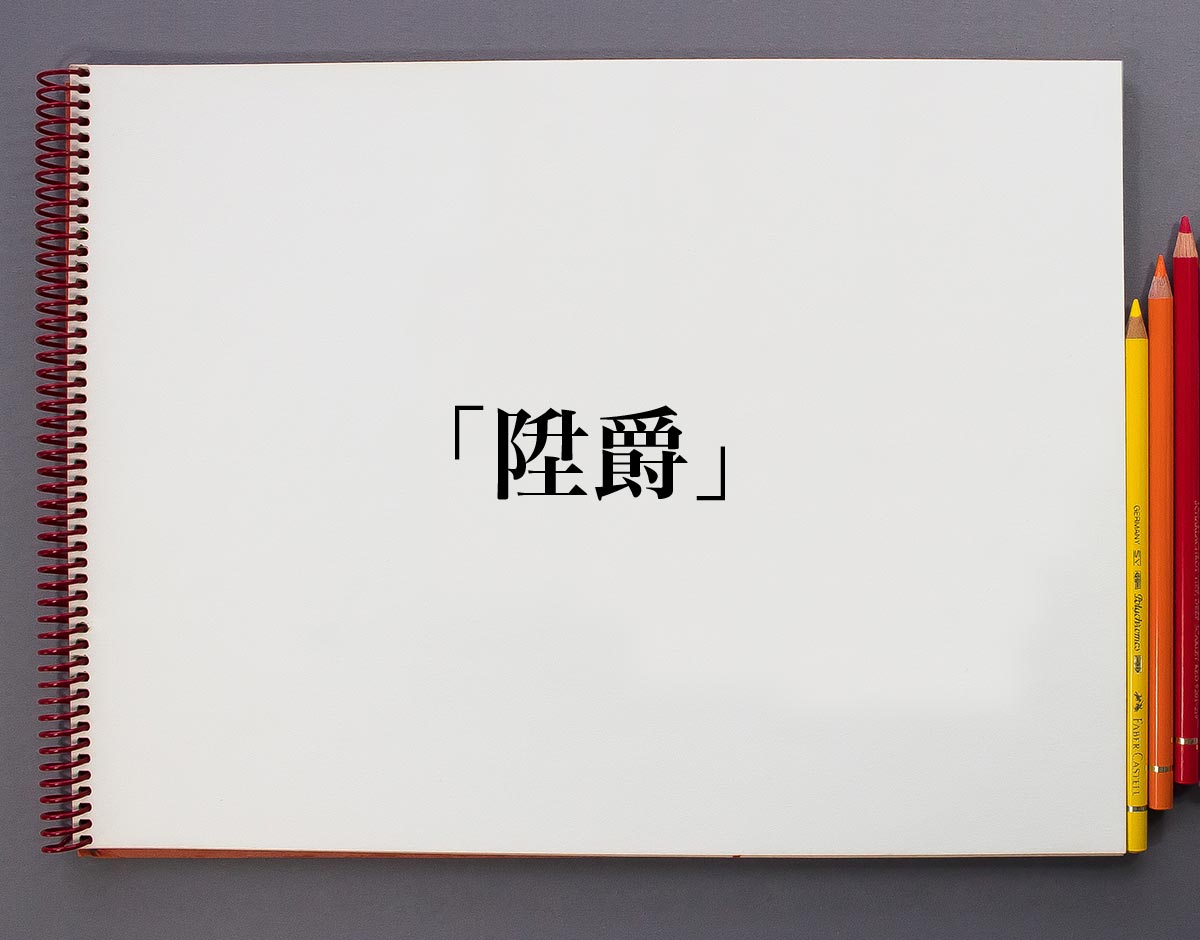「陞爵」
「陞爵」の読み方は、「しょうしゃく」になります。
「陞爵」の意味は、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」の五等爵の爵位制度で、男爵から子爵、子爵から伯爵のように「爵位が上がること」になります。
「陞爵」は爵位制度が廃止された現代では、ほとんど見かける機会のない言葉・漢字ですが、「爵位制度における昇進・格上げ」を意味する言葉です。
「陞爵」の「陞」という漢字は「昇」とほぼ同じ意味を持っていて、「陞」の音読みは「ショウ」、訓読みは「陞る(のぼる)・陞す(のぼす)」になっています。
「陞」は「昇」と同じで、地位の上昇を意味する漢字です。
そのため、組織内で地位が上がることを示す「昇進」は「陞進(しょうしん)」と書き換えることが可能です。
「陞爵」の類語・類義表現
「陞爵」の類語・類義表現には、どのようなものがあるのでしょうか?「陞爵」の類語・類義表現について、分かりやすく解説していきます。
「地位の昇進・役職の昇進」
「陞爵」の類語・類義表現には、「地位の昇進・役職の昇進」があります。
「陞爵」とは爵位制度において、男爵から子爵、子爵から伯爵のように爵位の身分が上昇することを意味しています。
そのことから、「陞爵」とほぼ同じ意味の類語として、「地位の昇進・役職の昇進」が上げられます。
「爵位の上昇・身分の昇格」
「陞爵」の類語・類義表現として、「爵位の上昇・身分の昇格」があります。
「陞爵」というのは、爵位制度における身分が上昇(昇格)することですから、その直接的な類義表現として「爵位の上昇」を指摘することができます。
「爵位の上昇」とは「身分(地位)の昇格」を意味していますから、「陞爵」の類義表現として「爵位の上昇・身分の昇格」を上げることができるのです。
「出世・栄進」
「陞爵」の類語・類義表現として、「出世・栄進」があります。
「陞爵」とは爵位の身分が上昇することであり、これを現代風に言い換えると「(企業・組織における)出世」になります。
「出世」とほぼ同じ意味合いを持つ言葉として、地位・身分が上がることを意味する「栄進(えいしん)」もあります。
「陞爵」の言葉の使い方
「陞爵」の言葉の使い方は、明治時代に存在していた華族令(旧爵位制度)において昇進した時に使うということになります。
具体的には、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」の五等爵の爵位制度で、男爵から子爵、伯爵から侯爵のように爵位が上昇(昇進)する時に、「陞爵」という言葉を使用することができるのです。
また、「陞爵」という言葉は日本の旧爵位制度だけではなく、ヨーロッパに残っているイギリス(英国王室)の爵位制度などにおいても使用することができます。
一般的に「陞爵」は貴族がほぼいなくなった現代ではあまり使われない言葉であり、「歴史上の爵位上昇の出来事・爵位が上昇した人物」を指して使われることが多いのです。
「陞爵」を使った例文・短文(解釈)
「陞爵」を使った例文・短文を紹介して、その意味を解釈していきます。
「陞爵」の例文1
「陞爵の言葉を理解するためには、明治時代にヨーロッパの貴族制度をお手本にして定めた爵位制度(五等爵)の「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」
を知っていなければなりません」この「陞爵」を使った例文は、爵位身分が上昇することを意味する爵位を具体的にイメージするためには、「華族令・爵位制度(五等爵)」について知っていなければならないことを意味しています。
「陞爵」の例文2
「日本には欧州的な華族令・五等爵制度が定められる以前から、朝廷の律令制・位階を前提にした陞爵の事例が多くありました」
この「陞爵」を使った例文は、近代以前の日本にも陞爵の事例があったこと、その陞爵は朝廷の律令制・位階(左右大臣などの官職)を前提にしていたことを意味しています。
「陞爵」の例文3
「子爵から伯爵へと昇進した先祖の陞爵の功績・栄誉は、我が家で100年以上にわたって語り継がれています」この「陞爵」
を使った例文は、我が家では先祖の陞爵(先祖が華族であり身分が上がったこと)の栄誉について、長く語り継がれているということを意味しています。
「陞爵」の例文4
「身分制度が廃止された現代の先進国では、陞爵という言葉は死語化しつつあります」
この「陞爵」を使った例文は、公爵や伯爵、男爵といった爵位が廃止された現代の多くの先進国・共和主義政体では、「陞爵の言葉」を知っている人や使っている人が大幅に減っていること(=死語化していること)を意味しています。