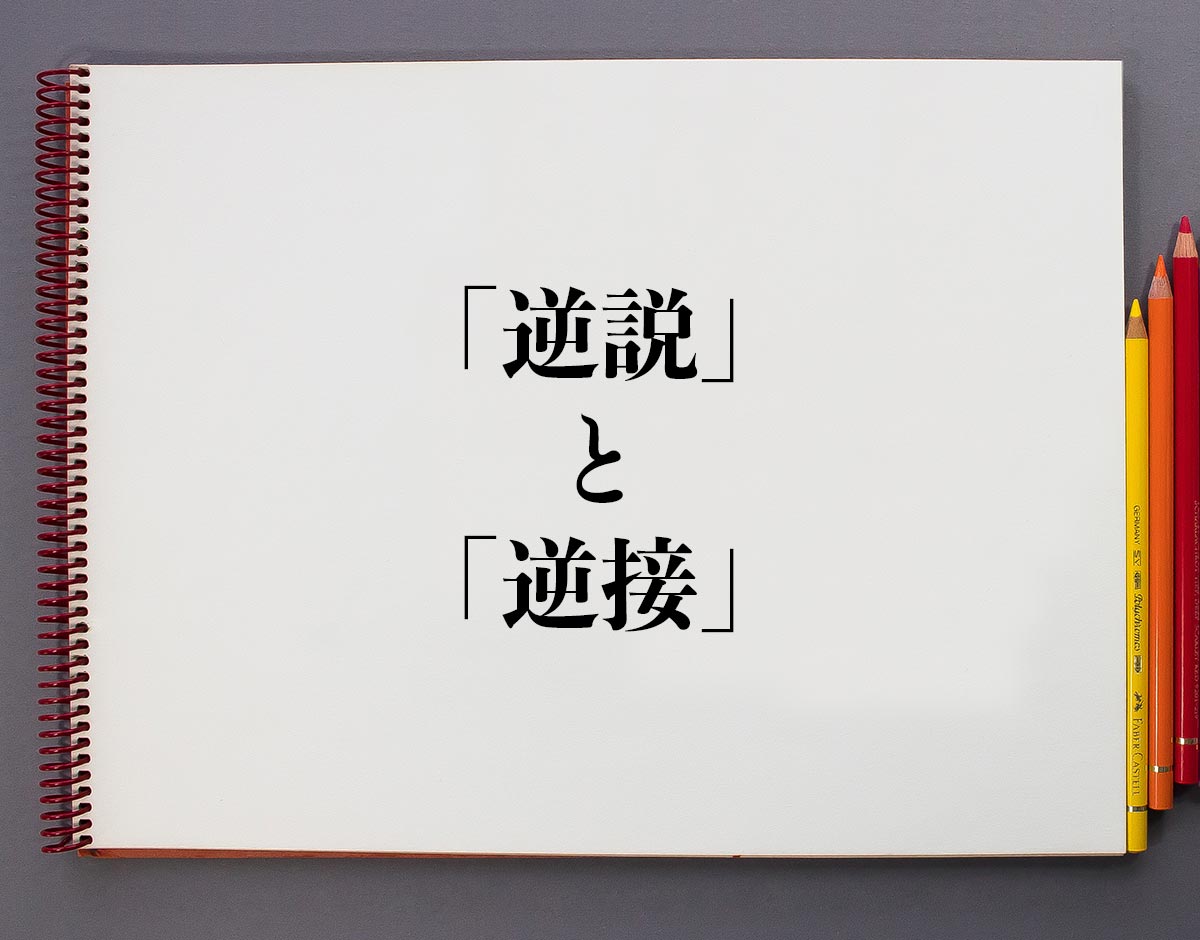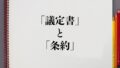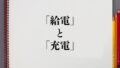この記事では、「逆説」と「逆接」の違いを分かりやすく説明していきます。
「逆説」とは?
「逆説」は「ぎゃくせつ」と読みます。
「逆」という漢字は、「物事の順序や進行の方向が反対になる」という意味を含んでいます。
「説」は「人に物事のすじみちを話して自分の意見に従わせる」「ときすすめる」といった意味があります。
この字から構成される「逆説」は「真理に背いているようで、よく考えると一種の真理を言い表している表現方法」「逆理」という意味になります。
「逆接」とは?
「逆接」も「ぎゃくせつ」と読みます。
「逆」の字は前述したとおり、「物事の順序や進行の方向が反対になる」という意味を含んでいます。
そして「接」は、「まじわる」「まじえる」「つづく」「つぐ」や「ちかづく」「ちかよる」という意味を持っています。
「逆」と「接」で構成される「逆接」とは「二つの文、または連文節の接続の仕方で、前項と後項との間に、矛盾、対立する要素があるものとして結びつける形式」のことをいいます。
わかりやすい例で説明すると「春になったけれど寒い」の「けれど」のような、「けれど」「しかし」で表される関係のことです。
「逆説」と「逆接」の違い
「逆説」とは「一見すると間違えているように思えるが、じっくりと考えてみると間違っていない考えや表現」のことをいいます。
一方「逆接」のほうは二つの文、または句の接続詞のことです。
「逆接」を使うことによって、先に述べた文から予想されるものと反対の結果を表現することができます。
前述した「春になったけれど寒い」の例を使って具体的に説明します。
「春になった」に続くのは一般的に「寒い」ではなく「暖かい」と予想されます。
通常は「春になったので暖かい」となりますが、「けれど」という「逆接」を使うことにより「春になったけれど寒い」という反対の結果を表すことができます。
反対の結果を表すための「しかし」「けれど」「だが」などが「逆接」です。
「逆説」と「逆接」は読みが同じですが、使い方や意味は全く違います。
「逆説」の例文
・『逆説的に言えば、彼は正しい』
・『そして逆説的ですが じっくりと時間をかけて解決するのです』
・『ここで逆説的にその新しい問題は簡単に解けると仮定する』
・『逆説的に、こうした社風が作品に影響しているともいえよう』
「逆接」の例文
・『逆接の接続詞「ばってん」などを用いる』
・『標準語の接続助詞ではないので逆接の意味は持たない』
・『逆接の接続助詞』
・『「ばってん」は逆接「しかし」「しかしながら」「だろうけれども」の意』
まとめ
以上が「逆説」と「逆接」の違いになります。
「逆説」は「一見すると間違えているように思えるが、じっくりと考えてみると間違っていない考えや表現」。
そして「逆接」とは「しかし」「けれど」「だが」などの句の接続詞です。
読み方は同じでも使い方や意味は全く違うということが分かりました。